運営メンバーの4人(北久保、米満、尾﨑、片瀬)が、青山学院大学・法政大学で教員として詩の授業を担当されていた、四元康祐先生にインタビューを行ってきました!
四元先生の詩を始めたきっかけから、詩を書く学生へのアドバイスまで、余すところなくお伝えします!今日は第2回目です。(全4回)
Q.四元先生はどのようなスタイルで下書きと推敲をしていますか。
僕は基本的に、手書きはしません。昔はワープロ、今だったらパソコンで書きますね。あの白い液晶画面の上に、明朝の活字が浮かび上がってくるのが僕の下書きのスタートですね。
若い頃はほとんど推敲をしませんでした。当時僕はタバコを吸っていたし、書くのが夜中だったので、もうもうと煙の広がっているところで一気呵成に書いていました。それを読み返して直すということは、ほとんどしなかったですね。詩集にするときにさすがに読み返しますが、そのときも直すのではなく、捨てるか、詩集に入れるかのゼロかイチかで編んでいくタイプでした。
下書きの仕方は未だに活字派ですが、推敲に関しては大きく変わったんです。第1稿を書くよりも、それを何度も何度も読み返して、いじっているときが一番楽しいんです。ものすごく微妙なところを、盆栽をいじるように直すんです。それで明らかに詩は良くなると思いますね。そのことを教えてくれたのは谷川俊太郎さんでした。師匠づらとかは絶対にしない人だから、すごく控えめに「その詩はあまり見せないほうがいいんじゃないかな…」というように言うんです。かえってそっちのほうがグサッと来るのですが、「自分の詩を読み返してみたらいいよ」ということを言ってくれて、何度も何度も読み返すようになりました。
〇3種類の推敲
僕の場合は3種類くらい、推敲のアプローチがあります。一つは、朝書いたら夕方に読み返して、ちょこちょこと推敲します。でも、まだ朝書いたときの意識を引きずっているので、書いている途中のような感覚です。
次に、2〜3日や1週間ほど経って、別のものを書くと、完全に1回忘れるわけです。忘れたときに見ると、この行はなかなかいいんじゃないかとか、もう恥ずかしいからカットしよう、ということが分かってきます。
3番目は、1年2年3年経って、完全に忘れてから他人のものとして読んでみるんです。そこで直すのは、それをもとに新しく書き直す、書き始めるような感覚です。
僕の中で一番大切なのは、2番目です。だから詩を書くとき、僕は毎日書きます。ある日書いたものを、次の日忘れるために別のものを書いて、それでまた前の詩に戻ってちょっと見て、次の日に書いた詩を忘れて…。こうやって積み重ねて、行ったり来たりしながら、作り上げていきます。
Q.詩をつくる最初の段階で詩集を意識されるのでしょうか。
『笑うバグ』は、構成を考えて詩を書きました。金融や経済、そして、それを支えているテクノロジー(シュレッダーとかコピーマシーンなど)、その中で翻弄されている人間(タイピストや掃除婦など)。システムとテクノロジーと人間、これらを組み合わせて1冊の詩集という構造物を作って、現代世界を表現できないかと考えました。常に明確なテーマがあって、それに即してひと月くらい、1日1篇ずつ書いて、50篇とか60篇とかから半分くらい出来のいい詩を選んで、というようにやってきました。
最近はそれも飽きてきちゃって、コンセプトも何もなしで詩を書くのが今は楽しいです。ですが、おのずとやはり同じ時期に書いているものは、一つの傾向とか、主題やスタイルを持っているので、それを組み合わせて一つの詩集にするというようなことになりつつあるかもしれないですね。
四元康祐(よつもとやすひろ)詩人
主な近書に、詩集『ソングレイン』『シ小説・鰾膠(にべ)』、訳詩集『ミャンマー証言詩集『いくら新芽を摘んでも春は止まらない』、エッセー集『詩探しの旅』など。2025年3月をもって、青山学院大学と法政大学の「詩の授業」の講師を「卒業」。
(文責:北久保 七海)
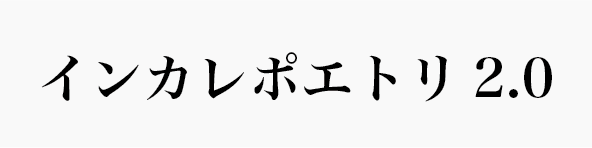

コメントを残す