運営メンバーの4人(北久保、米満、尾﨑、片瀬)が、青山学院大学・法政大学で教員として詩の授業を担当されていた、四元康祐先生にインタビューを行ってきました!
四元先生の詩を始めたきっかけから、詩を書く学生へのアドバイスまで、余すところなくお伝えします!今日は第1回目です。(全4回)
Q. 四元先生が詩を書き始めたきっかけはなんでしょうか。
僕が詩の道にはまったのは中学2年生で、中原中也を読んだときからです。もう既に中3の頃からは書いていたと思います。けれども、全然満足はできませんでした。
書いた詩が初めて活字になったのは、上智大学新聞の詩のコンクールで2等賞になった「笑顔とブランコ」という詩でした。大学新聞にそれが発表されて、その頃付き合ってたクラスメイトの女の子へのラブポエムだったから、すごく嬉しかったんです。ラブレターを書かなくても、それを読んでくれたらもう想いが伝わるみたいな。詩として書こうとした詩というよりも、リアルな目的をもって、他者を意識して書いたから、ふだんよりもいい詩が書けたんだと思います。ちなみに、それが今の妻です。
本格的に詩を書き始めたのは、1986年に日本を出て、アメリカで1年を過ごしてからです。26か27のときでした。日本から何冊か日本語の本を持っていったけど、全部読んでしまって、また自分でも書くかという気持ちで始めました。そのときは、英語で書いたんです。たどたどしい英語。それを日本語に自分で直したら、それが何か「あ、詩になってる」と思ったんです。
〇第一詩集『笑うバグ』
当時僕はアメリカで働きながら大学に行って、その後2年間、MBAというフルタイムの学生になりました。20代後半になって、学生生活が2年間できて、すごく時間が自由になったんです。そのときに、昼間学んだMBAの学科の内容を詩にしていきました。元々英語で学んだことを日本語に翻訳するということで、言葉と自分の意識のあいだにちょっと距離をあけるということができました。また、1980年代の半ば以降といえば、グローバル資本主義のようなものが広がっていく時代でした。地球全体が資本の論理によってのっぺりと平準化されてしまうそういう世界は、日本の詩歌ではうたわれたことがなかったので、詩にしたら面白いんじゃないかと思って始めたものです。
元はアメリカのビジネスや経済学や金融学の教科書や講義なんですが、それを東京で働いているOLの目線だったり、夜中のオフィスを片付ける掃除婦の立場だったり、日本の会社をベースにして書いています。僕が想定していたタイトルは『日本経済新聞への脚注』という、日本経済新聞に代表される経済やビジネスの社会を裏側から茶化す意図をもって書いた詩集です。ですが、出版社の人に、「そんなタイトルじゃ売れないから」と言われて、『笑うバグ』にしました。「バグ」というのは、コンピュータのシステムに入り込んだ、それを錯乱させる異分子、そういうものとしての詩や詩人ということでつけました。実は今でも満足していなくて、『日本経済新聞の脚注』にすればよかったと思っています。
〇大きな事件ーパーソナルワープロの登場
日本から出て、日本語と少し距離を置くことになって、戯れに英語で書いたものを翻訳したら詩のコツをつかんだという話をしましたが、同時にそのとき生じていた、非常に僕にとって大きな事件がありました。パーソナルワープロというものが当時世に出てきたんです。
日本の詩人には、それまで手書きしかありませんでした。ヨーロッパやアメリカの人は、手動のタイプライターがあって、自分の肉筆や肉声が活字になって、白い紙に打ち出されるという経験を幼いころからやっているわけです。しかし、日本の人はなんと1980年代まで、新聞や学校のガリ版などはありましたが、個人的なツールとしてはなかったわけです。それがようやく登場しました。
当時僕が使っていたのは、カシオかなにかのパーソナルワープロで、液晶ディスプレイに10字くらい、ほんの1行だけ表示されているようなものでした。これが僕にとって画期的でした。僕は字が下手だから、どんな詩を書いても下手に見えちゃうんです。でも、活字になると、客観的に読めるんです。自分の詩の言葉を、自分の肉体の続きで、肉体性みたいなものを持って見るのではなく、一回スパンと断ち切られて、すごく抽象的な明朝体でみられる。ここでも「距離を置く」ことで、書きやすくなりました。
僕が詩を本格的に書くようになったきっかけは、英語とワープロなんです。
四元康祐(よつもとやすひろ)詩人
主な近書に、詩集『ソングレイン』『シ小説・鰾膠(にべ)』、訳詩集『ミャンマー証言詩集『いくら新芽を摘んでも春は止まらない』、エッセー集『詩探しの旅』など。2025年3月をもって、青山学院大学と法政大学の「詩の授業」の講師を「卒業」する予定。
(文責:北久保 七海)
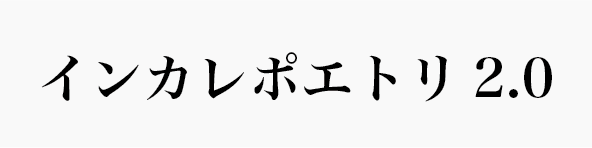

コメントを残す