運営メンバーの4人(北久保、米満、尾﨑、片瀬)が、2024年度まで青山学院大学・法政大学で教員として詩の授業を担当されていた、四元康祐先生にインタビューを行ってきました!
四元先生の詩を始めたきっかけから、詩を書く学生へのアドバイスまで、余すところなくお伝えします!第4回目、いよいよ最終回です。(全4回)
Q:個人的な話を書いた、伝わらない詩になってしまったり、逆に分かりやすすぎて面白みのない詩になってしまいます。
どこかで読んだような詩や決まり文句を連ねたような、分かりやすすぎる詩を書いてしまうことだって、特に最初の頃は、よくありますね。その反対に、一見分かりにくそうに見えるけど、それがただ難解さを装っているだけで、その演出が陳腐な詩などは、これはこれで読む気がなくなります。かといって、本当に何が書いてあるのか分からないものも読むのがつらい。誰にでもわかる、明快で透明な言葉で書きながら、これまで誰も見たことのない世界に連れて行ってくれる詩が理想です。
〇伝わらない詩/分かりやすすぎる詩へのアドバイス
もともと自分の中に物語があって、それを語るために詩を書くという人がいますね。それを語るために生まれてきたみたいな、本物の詩人タイプですね。ただ、その人の詩人としての技量がある水準に達していていないと、自分だけの世界でオタクになって、伝わらない詩になってしまう。そういうタイプの人に対してのアドバイスを、この前亡くなった谷川俊太郎さんが、伊藤比呂美さんとの対談(*)の中でやっていました。伊藤さんが「あと5分で詩の書き方を教えて」と言うんですね。伊藤さんは長いものを書くので、短いものを書くのが苦手なんです。ところが見開きで詩を頼まれて、どうやって書けばいいのか谷川さんに聞いているわけです。
谷川さんが「まずは、普段書いてるみたいに、ダーッと長く散文で、何ページでも書いてみりゃいいんだよ」と言うんです。そのあとで読み返して、適当に「ここ使えそうだっていうのをハサミで切ってきなさい」と。それを紙に貼っていくんです。何行か断片的な言葉があったり、またはワンパラグラフぐらいの散文があってもいいだろうし。次にその散文を、切り貼りにして、取捨選択したり、順番を入れ替えたりするんです。風穴が開いて風通しの良い、そういう構築物を作っていけばいいんじゃないか、と。
伊藤さんは、「そうすりゃいいんだ」と喜びます。ですが、伊藤さんが鋭いのは、「ダーッと書いてある中のどこをちょん切るかっていうこの選び方は、自分が気に入った箇所じゃ駄目でしょう」って言うんです。谷川さんが「その通り」と。そこで自分が気に入ったところを切り取っていくと、これまた自己表現の跡形がベタベタついたような詩になっちゃうから、そのときは自分のことを忘れて、誰でもいいから、誰か他の人のことを考えて、「これだったらあの人は喜んでくれるだろう」とか、「これだったら彼はウケるだろう」とか、とある特定の読者を想定することが大切です。自分の中の深い物語を大切にしながらも、そこから一歩抜けていって、より普遍的なところに届いて、みんなと分かち合えるということ。すごく大切なことだと思います。
*『対談集 ららら星のかなた』(谷川俊太郎/伊藤比呂美 著、中央公論新社)pp.141~146
四元康祐(よつもとやすひろ)詩人
主な近書に、詩集『ソングレイン』『シ小説・鰾膠(にべ)』、訳詩集『ミャンマー証言詩集『いくら新芽を摘んでも春は止まらない』、エッセー集『詩探しの旅』など。2025年3月をもって、青山学院大学と法政大学の「詩の授業」の講師を「卒業」。
〈編集後記〉
北久保:短い時間のインタビューでしたが、非常に楽しくお話を聞かせていただきました。また、その後も記事の執筆から校正まで、大変勉強になりました。
そして、読者の方からコメントをいただけたことも励みになりました。全4回に収まりきらなかったお話もたくさんあるので、それもいつか何らかの形でお届けできたらと思います。
最後になりますが、四元先生をはじめ、関わってくださった全ての方に感謝申し上げます。
米満:インカレポエトリ2.0最初のインタビュー記事、いかがだったでしょうか。2025年度以降も皆様に楽しんでいただけるような記事・企画をお送りできればと思います。
四元先生につきましてはご多忙な中インタビューをお引き受けいただき、大変ありがとうございました。
尾﨑:四元先生のお考えや感覚に様々な角度から迫れた貴重な会でした。
詩人の先生方がおっしゃることは、言葉は違えど同じことを指していると感じる瞬間が多く、何かそうした真理があるのかもしれないと思います。
どの質問にもフランクに真っ直ぐにお答えくださった四本先生に、改めて感謝申し上げます。
片瀬:四元先生の詩作の折々から自分と言葉のあり方にも向き合い直す貴重な経験をさせていただきました。「書く快楽」。きっと言葉を、詩を愛する私たちの中にもあるのだろうな、と思います。
(文責:北久保 七海)
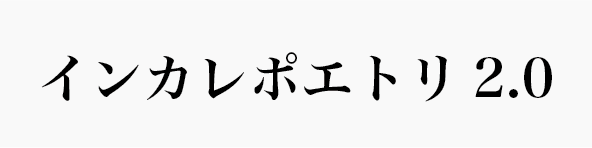

コメントを残す