運営メンバーの4人(北久保、米満、尾﨑、片瀬)が、青山学院大学・法政大学で教員として詩の授業を担当されていた、四元康祐先生にインタビューを行ってきました!
四元先生の詩を始めたきっかけから、詩を書く学生へのアドバイスまで、余すところなくお伝えします!今日は第3回目です。(全4回)
前半はこれまでの内容をまとめ、後半は学生からの詩作の悩みに答えていただきます。
—お話を聞いていて、言語と書く媒体、それに加えて時間的な距離というのが、四元先生のなかで重要なものとして出てきているように感じます。
〇詩人の2つのタイプ
僕はどちらかというと突き放すタイプだから、あの手この手で、時間的に、言語的に、そしてメディア的に切れ目を入れたいんでしょうね。つくづく、自分がディタッチメントの詩人だなと思いますね。
詩人のタイプに、アタッチメント型とディタッチメント型とがあると思うんです。
アタッチメント型は、感情移入して一体になって詩を「書く」タイプ。徹底的に自分にこだわって、自分のことを洗いざらい書いて、自分を乗り越えて普遍的なものに達するような書き方です。伊藤比呂美さんとか、白石かずこさんとかですね。
ディタッチメント型は、突き放して詩を「作る」タイプ。最初から自分というものがないような書き方をして、自分を消すことで万人になっていくような書き方です。新川和江さんや谷川俊太郎さんですね。自己と何かが切れていることが大切なタイプの詩、詩人です。
どっちにしたって普遍的なものに立ち到りたいわけです。この2つのタイプは、詩というものをどう捉えているかという本質に関わる、詩人の資質みたいなものだと思います。
Q:四元先生はどういった方を読者として想定して詩を書かれるのでしょうか。人によっては「客観的な読者」を想定して書くということも聞きますが、自分にとっての他者は、ある程度普段付き合いのある人で構成されるので、自分から離れることが難しく感じます。
僕にとっての他者は、架空の親戚のおじさんです。このおじさんは詩とかも読んだことがないのですが、結構いい人なんです。詩を書き始めたころから、常に僕の中にいますね。何かを書いたときに、このおじさんに見せたり、おじさんの前で自分が朗読して恥ずかしくないかどうかが大きな基準になっています。おじさんに、なに気取ってるんだ、と言われないものを書きたいという思いがすごくありますね。
〇書く快楽
僕自身はあまり個人的なことは書いていません。書くものは偶然というか、何でもいいんです。とりあえず朝起きて目の前に物体があって(机の上のペットボトルを指す)、何か影があるなと思って、その一行を書いて、発想をベタにつなげたり、飛躍させながら二行目を書く。するとそこにおのずと文脈のようなものが現れますね。三行目は、その文脈を素直に展開するのか、それともそこでポンと飛躍させるのか、あるいは何か反論みたいなひっくり返すのかっていう選択が迫られるわけですね。でももう三行も書けば、詩はほとんど出来上がったようなものです。最初の一行を選ぶのはかなり直感と偶然ですが、二行目以降は自分の中に書く人と編集する人が共存しているような、知的な操作になります。
問題は、終わりの方です。その詩の終わりをどうするかは、これまた最初と同じで、ある種の霊感を待つしかないですね。僕は、無理やり終わらせようとせずに、尻切れトンボの後味の悪い感じを丁寧にポケットに入れて、単純作業をします。アイロンをかけるとか、洗濯物を取り込むとか、お皿を洗うとか、便所掃除をするとか。そういう作業をしてると正解が見つかるんですね。その詩の終わらせ方というか、息の根の止め方が。これはやはり理性を超えたところから降りてくるのを待つしかないですから。時にはそれが何日もかかることもあるんですけれども、でも大抵は何か単純作業をしてると、虚を突かれるような行が降りてきます。それがきっかけでまたちょっと元に戻って変えたりもしますけどね。
基本的に僕には言いたいことがないんです。書きたいことや言いたいことがあるわけではなく、書く快楽しかないんです。
次回に続く
四元康祐(よつもとやすひろ)詩人
主な近書に、詩集『ソングレイン』『シ小説・鰾膠(にべ)』、訳詩集『ミャンマー証言詩集『いくら新芽を摘んでも春は止まらない』、エッセー集『詩探しの旅』など。2025年3月をもって、青山学院大学と法政大学の「詩の授業」の講師を「卒業」。
(文責:北久保 七海)
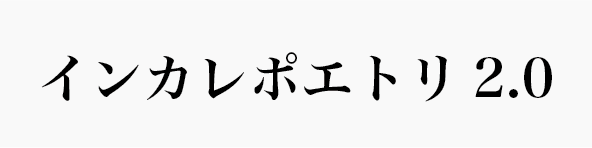

コメントを残す